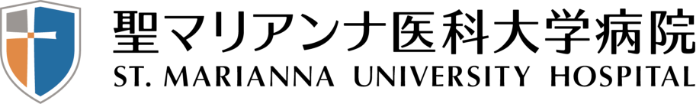病名検索
疾患・症状のご紹介
疾患概要
肺高血圧症とは
肺高血圧症は、肺の血管や心臓(右心系)に負担がかかり、息切れ・動悸・むくみなどを引き起こす病気です。比較的稀な病気のため初期は診断に至りにくい一方、この20年で治療は大きく進歩し、適切な診断と治療により見通しの改善が期待できます。
当院では、早期診断・早期介入と個別最適化された治療を軸に、症状の軽減と長期的な健康維持をめざします。大学病院・総合病院の強みを活かし、膠原病・呼吸器疾患・肝疾患など関連領域と密に連携します。
「肺高血圧症かもしれない」段階からのご相談も歓迎しています。また、現在肺高血圧症治療中の患者さんについても、「肺高血圧症を専門とする担当医が不在となった」など、何らかの理由で専門施設でのフォローアップ検査や評価をご希望される方は遠慮なくご相談を頂ければと思います。
こんな症状はご相談ください
- 階段や坂での息切れ・動悸の増加
- 足のむくみ、体重増加(むくみによる)
- 胸の圧迫感・失神(ふらつき)
- 原因不明の疲れやすさ、運動能力の低下
診療の流れ
① 外来初診(スクリーニング)
- 血液検査/心電図/胸部レントゲン/心臓超音波(心エコー)
- 症状や病状に応じて運動負荷心エコーを追加する場合があります
② 精密評価(必要時)
- 肺血流シンチグラフィー(血栓の関与を評価)
- 肺高血圧症が強く疑われる・他院でスクリーニング済みの場合は、原則2泊3日の入院で右心カテーテル検査を行い、血行動態を精密に評価します
- 右心カテーテル検査では、以下を症状・状態に応じて組み合わせ、治療薬が合いそうか/原因は何かを詳しく調べます
○急性肺血管反応性試験(一部の薬が効きやすいタイプかを判定)
○生理食塩水負荷試験・ハンドグリップ負荷試験(左心疾患の関与などを評価)
③ 治療方針の決定とフォロー
- 結果をわかりやすくご説明し、患者さんごとの最適な治療計画を作成します
- 外来での薬剤調整と、定期的な診察・検査で効果と安全性を確認します
入院日数や検査スケジュールは、症状やご都合に合わせて柔軟に調整します。
薬物治療について
日本のガイドラインに準拠し、状態に応じて薬剤を1剤から複数併用まで個別に調整します。
- エンドセリン受容体拮抗薬
- PDE5阻害薬/可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬
- プロスタサイクリン受容体作動薬(内服・吸入・持続静注など)
- アクチビンシグナル伝達阻害剤(皮下注射) など
膠原病・呼吸器疾患・肝疾患などが背景にある場合は、各専門科と速やかに連携し、適切な治療介入を行います。心肺疾患合併の方も、病状に合わせて個別に最適な薬物治療を検討します。
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)とBPA
急性肺血栓塞栓症にかかったことのある患者さんのうち約5%は、慢性期に固くなった血栓が肺の血流を阻害するため、肺高血圧症を来します。この病態を慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)と言います。明らかな急性肺血栓塞栓症にかかったことのない患者さんでもCTEPHを発症することがあります。当院ではCTEPHに対して薬物療法に加えてバルーン肺動脈形成術(BPA)を行っています。
当院は日本循環器学会のBPA実施施設として登録されており、既に80件以上の治療を行っています。日本循環器学会に認定された実施医により安全な手技を心掛けています。
原則4泊5日で、治療前検査→BPA→治療後フォローまでを一連で行います。必要に応じて段階的に複数回のBPAを計画します。
よくあるご質問
- Q.右心カテーテル検査は痛いですか?
A. 多くは局所麻酔で実施し、強い痛みは少ない検査です。安全に配慮して行います。 - Q.仕事はどれくらい休む必要がありますか?
A. 右心カテーテル検査は原則2泊3日が目安です。BPAは原則4泊5日です。個別にご相談ください。 - Q.すでに他院でフォロー中でも受診できますか?
A. 可能です。専門評価のみや治療方針のセカンドオピニオンも承ります。 - Q.合併症(心疾患や肺疾患など)があっても治療できますか?
A. はい。関連診療科と連携し、薬剤選択や投与量を慎重に調整します。 -
受診・ご紹介について
- 紹介状あり/なしいずれもご相談いただけます(可能であれば紹介状をご用意ください)
- 044-977-8111(代表番号)より予約を取得してください
- 肺高血圧症・成人先天性心疾患専門外来:毎週金曜日13時〜17時
(ご都合が合わない場合は一般的な「循環器内科外来初診」でも対応可能です)
-
医療関係者の皆さまへ
- 早期診断・早期介入の観点から、肺高血圧症が疑われる段階でのご紹介を歓迎します
- 運動負荷心エコー検査・右心カテーテル検査、BPA適応評価のみのスポット受診も対応可能です
- 共同診療・逆紹介の運用は柔軟にご相談ください
対象の診療科