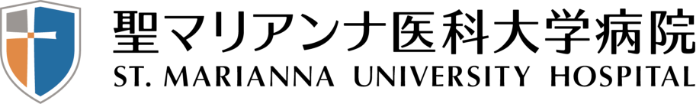小児科・新生児科
小児科・新生児科
ご挨拶
地域に根ざした基幹病院の小児科として地域とその住民の皆様の医療ニーズに応えることをモットーにしています。また、他の診療科およびコメディカルとの強い連携のもとに小児疾患の総合的な医療提供を目指しています。小児救急医療から専門性の高い臓器別医療を提供しています。
具体的に小児科は総合周産期母子医療センター、小児内科系病棟、小児外科系病棟の入院部門と、一般外来、専門外来(小児神経、小児呼吸器・アレルギー疾患、小児循環器、小児悪性腫瘍、小児血液疾患、内分泌代謝疾患、小児腎臓病、予防接種、発達外来、育児相談、遺伝相談)から成り立っています。また、救命救急センターとの協力で川崎市の小児三次救急を引き受けています。小児救急については川崎市立多摩病院小児科とホットラインで結び、緊密な連携のもとに高度な救急医療を提供しています。

診療部長
清水 直樹(主任教授)
平成22年3月より当院にて総合周産期母子医療センター(新生児ベッド36床、内NICU加算:12床)が開設し、川崎市および神奈川県の周産期、新生児医療の3次中核施設として、その機能がより強化されました。県内完結型医療を目標とする上で産科との協力体制は言うまでもありませんが、母体、胎児、新生児の救命救急の更なるレベルアップには、内科、外科など他科との連携がこれまで以上に重要となります。
附属病院である聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院(新生児ベッド:30床、内NICU加算9床)と協力し、小さくとも大切な命と、その命を見守る家族に優しい医療を提供していきたいと思います。

診療部長
北東 功(教授)
対象疾患
- ネフローゼ症候群、急性・慢性腎炎、急性・慢性腎不全、腎尿路異常、尿路感染症、夜尿症
- 低出生体重児、新生児疾患、新生児外科疾患
- 血友病、フォンヴィレブランド病、遺伝性血小板機能異常症、ITP、先天性血栓性疾患、抗リン脂質抗体症候群、遺伝性赤血球状赤血球症
- 熱性けいれん、てんかん、発達遅滞、重症心身障害児(者)
- 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫、脳腫瘍、神経芽腫など小児がん疾患
- 先天性心疾患、川崎病、心筋症、不整脈
- 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー
- 百日咳
- 成長に関する疾患、先天代謝異常症、甲状腺疾患、副腎疾患、小児糖尿病、小児生活習慣病
| 初診外来 | 再診外来 | 専門外来 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 午前 | 安蔵慎 | 宮本雄策 |
[神経・発達・てんかん外来] 岩﨑俊之 |
| 午後 | [乳児健診] ○北東功 鈴木真波 [発達児フォロー外来] ○北東功 鈴木真波 [成人先天性心疾患外来] △麻生健太郎(1,3) △近田正英 長田洋資 |
|||
| 火 | 午前 | △森鉄也 | △麻生健太郎 |
[在宅移行外来] [小児難治てんかん外来] |
| 午後 | [腎臓外来] 小林久志 生駒雅昭 村田俊輔 [腫瘍外来] △森鉄也 木下明俊(2,4) 慶野大(4) 近藤健介(不定月) [在宅移行外来] ○清水直樹 [先天代謝外来] 村山圭(4) 松永綾子 |
|||
| 水 | 午前 | △宇田川紀子 | 中村幸嗣 | [神経外来] 山本仁 [血液外来] 瀧正志(4) 長江千愛 山下敦己 足利朋子 森美佳 梅沢陽太郎 |
| 午後 |
[感染症・予防接種外来] 宮奈香 中島眞生子(2,4,5) |
|||
| 木 | 午前 | 森 美佳 | 栗原八千代 | [神経・発達・てんかん外来] 大松泰生 |
| 午後 |
[アレルギー外来] 木谷好希 塚原歩 伊東祐順 鹿野直樹 |
|||
| 金 | 午前 | 栗原八千代 | 長江千愛 | [遺伝外来] 右田王介 鳥飼美穂 小澤南 |
| 午後 | [心臓外来] △麻生健太郎 中野茉莉恵 長田洋資 [内分泌・代謝外来] 大串健一郎 曽根田瞬 |
|||
| 土 | 午前 |
交替制 |
交替制 | [内分泌外来] 大串健一郎(2,4,5) [神経・発達・てんかん外来] 岩﨑俊之(予約のみ)(2,4) [心臓外来] △麻生健太郎(2,4,5) |
| 午後 | ||||
〇=部長、△=副部長、[非]=非常勤
都合により変更になる場合があります。
午後は原則再診のみ(予約制)
( )内の数字は第何週目かを示しています。
休診・代診のご案内
現在「休診・代診のご案内」はありません。
主な手術および検査件数
(平成28年度実績)
| 手術名・検査名 | 件数 |
|---|---|
| ■腎生検 | 11 |
| ■心臓カテーテル検査 | 80 |
| ■造血幹細胞移植 | 2 |
| 同種移植 | 2 |
| 自家移植 | 0 |
研究内容
- 小児における抗リン脂質抗体症候群の臨床的特徴に関する研究
- 血友病のQOLに関する研究
- 出血性疾患、血栓性疾患のトロンビンジェネレーション、ROTEMなどの包括的凝固評価
- 小児各種疾患における酸化的ストレスマーカー(8-OHdG)の測定と脳障害児での検討
- 各種腎炎における活動性ケモカインの検討
- 百日咳菌流行株の遺伝子変異解析
- 慢性肺疾患の病態解明と治療法に関する基礎的検討
- 「母体へのステロイド投与による胎児への心・肺機能の影響」の実験的研究
- 産後うつ予防による育児支援についての系統的研究
- 各種小児がんに対する多施設共同疫学研究・臨床試験
- 小児難治性白血病に対する新規治療法の研究
- 小児リンパ腫に対する早期治療開発
- 成長障害や性分化異常に対する分子内分泌学的検討
- 各種予防接種後に起きる局所反応の病理組織学的研究
- 小児気管支喘息における呼吸機能検査の有用性
- 小児食物アレルギーに対する負荷試験の検討
成人先天性心疾患外来設立のご案内
先天性心疾患に対する外科ならびに内科治療の飛躍的な発展により、現在では約90%の先天性心疾患の患者さんが成人に到達するようになりました。先天性心疾患では幼少期に無事に手術を終えた場合でも術後の遠隔期に生じる心不全、不整脈や弁不全に対し内科、外科治療が必要となることもあり、術後の経過が良好であっても成人期以後までフォローが必要となることが多々あります。更に成人期に到達すると原疾患に加齢に伴う問題が加わり多彩かつ複雑な症状を呈するようになります。また結婚、出産、遺伝などの原疾患以外にも多岐に渡る問題を抱えるようになります。これまで先天性心疾患患者の診療は主に小児科医、小児心臓血管外科の医師が担当してきましたが多くの患者さんが成人期に到達するようになり、幼少時から診療を担当していた診療科の医師だけでは対処が困難な問題に直面するようになってきました。このような患者さんの問題に対しては小児循環器医師や心臓血管医師のみならず成人循環器内科、産婦人科、遺伝科などが協力して総合的に診療にあたる必要があります。
現在この分野の専門外来を設けている施設は未だ少なく患者さんもどの科を受診すべきであるのか困惑していることも多いかと思います。この問題に対処すべく私たちは成人先天性心疾患診療科を開設することにしました。大学総合病院の利点を生かし、各科が協力して成人先天性心疾患の患者さんに生じる様々な問題に対処できるようにしたいと考えています。
川崎地区てんかんネットワークについて
てんかんは、乳幼児から高齢者まで誰にでも起こりうる患者数の多い病気で、我が国の患者数はおよそ100万人とも言われています。その症状と治療法は様々で長期間に及ぶ医療・福祉ケアを必要とすることから、診療には小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科など様々な診療科の連携が必要とされています。
しかし我が国では、地域でどの医師がてんかん診療を行っているのかも分かり難く、多くの患者さんが専門的な医療に結びついていない可能性が示唆されています。こうした中、厚労科学研究班は全国規模のてんかん診療ネットワークを構築し、これまで分かり難かったてんかん医療へのアクセスポイントを明らかにし、より効果的に診療連携を推進するための新しいてんかん地域診療連携システムを提案しています。
川崎地区てんかん診療ネットワークはこうした試みに賛同し、地域の患者さんに適切な医療を提供すべく、自主的に連携しております。
小児がん治療や造血幹細胞移植を
受ける方への
妊孕性温存のご案内
小児期がん化学療法や放射線治療、造血幹細胞移植を受ける患者さんでは、治療により将来の妊孕性(妊娠できる能力)が損なわれることがあります。
当院では生殖医療センターと小児がん専門医の連携により、卵巣組織凍結保存や精子保存などにより妊孕性を温存する取り組みを開始しています。他の病院や施設で治療を受ける患者さんも妊孕性に関するご相談を受け付けます。
小児科腫瘍外来(毎週火曜日午後)へご相談ください。
診療科・部門のご案内
-
診療科
-
部門
-
センター
- 救命救急センター
- 夜間急患センター
- リハビリテーションセンター
- 健康診断センター
- 総合周産期母子医療センター
- 生殖医療センター
- 精神療法・ストレスケアセンター
- 腎臓病センター
- 腫瘍センター
- 内視鏡センター
- 超音波センター
- 画像センター
- 放射線治療センター
- 輸血部
- 臨床検査センター
- 手術・IVRセンター
- 集中治療センター
- 中央器材室
認知症(老年精神疾患)治療研究センター
- 統合失調症治療センター
- 呼吸器病センター
- ハートセンター
- 心不全センター
- ハイブリッド心臓大動脈治療センター
- 脳卒中センター
- パーキンソン病治療センター
- 肝疾患医療センター
- 脊椎センター
- 人工関節センター
- こどもセンター
- 内分泌疾患センター
- ゲノム医療推進センター
- 遺伝診療部
- がんゲノム診療部
- 緩和ケアセンター
- 感染症センター
- 糖尿病センター
- てんかんセンター
- 胆道・膵臓病センター
- リウマチ・膠原病生涯治療センター
- 神経内分泌腫瘍センター
- こどものこころセンター