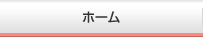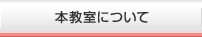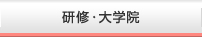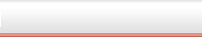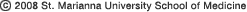メッセージ
ご挨拶

救急医学は、1998年創立の新しい講座である。1980年設立の救命救急センターの診療実績から、さらなる救急医療の発展には、救急医療の独自性と各科との協力・連携を担う核となる教室が必要であるとの認識から設立された。全国医大のなかで救急医学教室としての設立は早い。
医科大学の教室として、1.診療、2.教育、3.研究が責務である。
1. 診療:救命救急センターと夜間急患センターから、1次から3次まで総ての救急患者を受け入れてきたが、さらに統合ERとして新たな一歩を踏み出した。救命センター内30床の病棟において、EBMに基づき最新の機器を駆使した集中治療を実施し、独自のプロトコル作成も心がけている。
2. 教育:学生への従来の講義に加えPBL、BSLを実施。後期研修についてはその内容を本HPで参照されたい。
3. 研究:統合ERでの豊富な経験を基に、質の向上を目指した臨床研究を実施している。
新たな循環動態モニタリングとショックにおける組織酸素代謝異常をメインテーマとし、臨床研究と実験系での研究を行なっている。
沿革と展望
救急医療体制の整備計画として誕生した、第3次救急施設である当救急救命センターは、神奈川県内で一番最初にオープンしました(昭和55年7月1日)。その後、院内感染の防止と広範熱傷患者の治療成績向上のため、熱傷センターを併置しました(昭和58年10月1日)。 平成6年5月には、地域の中核病院としての使命を果たすべく、救急救命センターに夜間急患センターが併設されました。(夜間急患センターの診療時間は、18時から翌朝8時までです。)
明石勝也 現理事長が初代教授となり、平成11年11月より救急医学教室を開講され、救急専属医・救急スタッフも益々充実してきています。救命救急・熱傷センターは本学創立の精神「生命の尊厳」と「奉仕の精神」に沿い、診療域の一環として、これからさらに予測される高齢化を含めた社会福祉に寄与する救急医学を目指しています。
当医局は、聖マリアンナ医科大学附属横浜市西部病院、川崎市立多摩病院とともに、新たな後期研修プログラムを平成20年度より開始しました。プログラムの特徴として、4年間で、プライマリ・ケアから第3次救急まで幅広い症例数を経験でき、CCU管理を含めたICUトレーニングを受けることができます。トレーニング、豊富な症例数のみでなく、教育を重視したトレーニングとなっています。今後は、当プログラムより、優秀な人材を需要のある全国の施設に派遣できるよう、一路邁進していく所存です。
本教室について