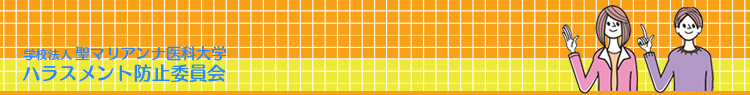| ① |
相談員は、相談者の訴えを直接聞き、事案の内容と状況を把握します。 |
| ② |
相談員は、相談者に対処方法等についての情報提供を行い、相談者が対処について自ら意思決定することを支援し、当事者及び関係者への事情聴取を行います。相談者等が希望する場合は、当事者等との間で調停を行います。 |
| ③ |
相談員で解決できない事案の場合及び修学・就業環境の改善等、何らかの措置を必要とすると思われる場合は、相談者等の了承を得て、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)へ相談概要を報告します。 |
| ④ |
委員会は、事実関係の調査の要否、再発防止措置の必要性等を協議します。 |
| ⑤ |
委員会が調査委員会を設置する必要がないと判断したときは、相談員に再発防止措置を指示します。 |
| ⑥ |
相談員は、委員会の指示内容を当事者に伝え、再発防止措置の履行を確認します。 |
| ⑦ |
調査が必要であると委員会が判断したときは、調査委員会を設置します。 |
| ⑧ |
調査委員会は、当事者から意見・異議・反論等聴取し、事実関係の調査を行い、その結果を2週間以内に委員会の委員長に報告します。 |
| ⑨ |
委員会は、調査委員会の報告に基づき、場合によっては学内外の専門家を交えて協議し、再発防止等の措置を決定します。 |
| ⑩ |
委員会の決定内容を相談員に指示し、相談員は⑥により当事者に再発防止措置の履行を確認します。 |
⑪ |
委員会は、関係者が懲戒処分等の対象になると判断したときは、学長に意見具申します。 |
| ⑫ |
学長は、懲戒処分等の対象者によって、教職員の場合は理事長に、看護専門学校生の場合は学校長に報告します。 |
| ⑬ |
理事長、学長、学校長は、学則、教職員勤務規則に基づき関係委員会等に懲戒処分について諮問し、懲戒処分等を決定します。 |