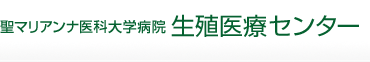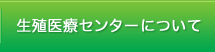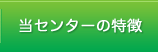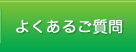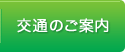- ホーム > 生殖医療センターについて > センター長ご挨拶
センター長ご挨拶

設置の目的
生殖医療センターは、この生殖補助技術を用いた治療を主に行う部門として設置されました。近年の生殖医療の進歩にはめざましいものがあります。生殖補助技術を行うには、専門的な知識・技術が必要です。大学病院の特性を生かし、専門的な手術や検査も行っています。当センターには、他の病院で断られるような合併症のある患者さんやなかなか妊娠に至らなかった難治性不妊の患者さんも多く受診されています。またこの治療は、カップル単位の医療であり当生殖医療センターでは男女両面からのサポートをする診療を心掛けています。このような高度医療を行うための診療科間の連携を保つために生殖医学の基礎研究者も本センターに加わり設立されました。またこのセンターは精子・卵を扱うことから本学の生命倫理委員会の管理下に運営されています。 センター長 鈴木 直 (教授)