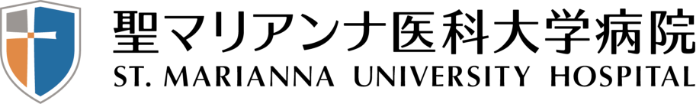腎臓・高血圧内科
腎臓・高血圧内科
| 主病棟 | 入院棟6階南 |
|---|---|
| 外来 | 病院本館2階東外来 |
| 対応疾患 | 尿の異常(蛋白尿、血尿、尿量異常など)、腎機能の低下(血清クレアチニン値上昇、尿毒症など)、腎形態の異常、尿路結石症、透析や高度腎不全に関する内科的諸問題、透析アクセス異常(シャントトラブルなど)透析療法(腹膜透析や在宅血液透析を含む)、腎移植、各電解質異常、酸塩基平衡異常、体液量異常(浮腫・脱水症など)、高血圧全般 |
ご挨拶
腎臓・高血圧内科では発症から末期腎不全に至るまでのすべての段階の腎疾患を対象としています。また高血圧は腎疾患と密接な関係がありますので、高血圧を診療のもう一方の柱とし、高血圧を適切に治療することにより患者さんの予後の改善に努めています。腎移植では内科と外科が移植チームを作って、長期生着を目指します。
大学病院の使命として臨床・教育・研究を推進し、医局員一丸となってより良い医療を提供できるよう尽力してまいります。

診療部長
柴垣 有吾(主任教授)
診療内容
- 腎炎・ネフローゼ症候群:腎生検
- 血液浄化療法:血液透析導入、特殊浄化療法(血漿交換、アフェレーシス)、在宅血液透析
- バスキュラーアクセス:アクセス造設(内シャント増設術、人工血管移植術、動脈表在化、長期留置カテーテル挿入術)、VAIVT
- 腹膜透析
- 腎移植
- 多発性嚢胞腎
- 尿路結石
- 高血圧
- 体液過剰
- 電解質異常
対象疾患
以下でお困りの場合は、是非、当科までご紹介下さい。
腎疾患
- 尿の異常(蛋白尿、血尿、尿量異常など)
- 腎機能の低下(血清クレアチニン値上昇、尿毒症など)
- 腎形態の異常
- 尿路結石症
透析・高度腎不全の諸問題
- 透析や高度腎不全に関する内科的諸問題
- 透析アクセス異常(シャントトラブルなど)
- 透析療法(腹膜透析や在宅血液透析を含む)や腎移植の検討や選択が必要な方
体液・電解質異常
- 各電解質異常(Na, K, Ca, P, Mgなど)
- 酸塩基平衡異常
- 体液量異常(浮腫・脱水症など)
高血圧疾患
- 高血圧全般
| 初診外来 | 再診外来 | 専門外来 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 午前 |
麻生芽亜(1,3,5) 谷澤雅彦(2,4) |
〇柴垣有吾 市川大介 |
[腹膜透析/在宅血液透析外来] [腎代替療法説明外来] 谷澤雅彦(交替制) 山田将平(交替制) 櫻田勉(交替制) |
| 午後 |
吉田圭佑 北野史也 |
[腹膜透析/在宅血液透析外来] [腎代替療法説明外来] 谷澤雅彦(交替制) 山田将平(交替制) 櫻田勉(交替制) |
||
| 火 | 午前 |
韓 蔚(1,3,5) 久道三佳子(2,4)
|
谷澤雅彦 緒方聖友 |
[バスキュラーアクセス外来] 市川大介 田邉淳(1,3,5) 山田将平 小波津香織 湯浅千晶 [腎代替療法説明外来] 小波津香織(交替制) 松田拓也(交替制) |
| 午後 |
山田将平 |
[尿路結石外来] 渡邉詩香(1,3,5) 白井小百合(2) 田邉淳(2,4) [腹膜透析/在宅血液透析外来] 山田将平 小波津香織 湯浅千晶 [腎代替療法説明外来] 小波津香織(交替制) 松田拓也(交替制) |
||
| 水 | 午前 | 若松俊樹 |
△櫻田勉 渡邉詩香 |
[腹膜透析外来] [腎代替療法説明外来] 田邉淳 湯浅千晶 |
| 午後 | 麻生芽亜 |
[腹膜透析外来] [腎代替療法説明外来] 田邉淳 湯浅千晶 |
||
| 木 | 午前 |
柴垣有吾( 1,3,5) 市川大介(2) 櫻田勉(3) |
韓蔚 小波津香織 |
[腎移植外来] 8:30~11:00 谷澤雅彦 緒方聖友 宮内隆政 [腹膜透析外来] 小島茂樹 |
| 午後 | 松田拓也 |
[腎炎外来] 市川大介(1,3,5) 韓蔚(2,4交替制) 鈴木智(2,4交替制) |
||
| 金 | 午前 |
小波津香織(1,3,5) 渡邉詩香(2,4) |
久道三佳子 田邉亮 |
[腎移植外来] 8:30~11:00 谷澤雅彦 |
| 午後 |
湯浅千晶 白井佳那 |
[腎移植外来] 谷澤雅彦 |
||
| 土 | 午前 |
小山亮(1) 麻生芽亜(2) 佐藤歩(3) 若松俊樹(4) |
池森敦子(2,4,5) 白井佳那(1,3交替制) 北野史也(1,3交替制) 市川滉介(1,3交替制) 湯浅千晶(1,3交替制) |
[腎移植外来] 緒方聖友 [腎代替療法説明外来] 小島茂樹(交替制) 小波津香織(交替制) [嚢胞腎外来] |
| 午後 | ||||
〇=部長、△=副部長、[非]=非常勤
都合により変更になる場合があります。
午後は原則再診のみ(予約制)
( )内の数字は第何週目かを示しています。
休診・代診のご案内
現在「休診・代診のご案内」はありません。
| 手術名・検査名 | 件数 |
|---|---|
| ■腎生検 | 111 |
| ■透析方法別_維持浄化療法導入件数 | |
| 体外循環式 | 71 |
| CAPD | 7 |
| ■原疾患別_維持浄化療法導入件数 | |
| 慢性腎炎 | 7 |
| 糖尿病 | 27 |
| 腎硬化症 | 24 |
| 多発嚢胞腎 | 4 |
| その他 | 16 |
| ■在宅血液透析 | |
| 新規導入 | 0 |
|
維持在宅血液透析 |
2 |
| ■体外循環式血液浄化療法件数 | |
| 血液透析 | 4680 |
| 限外濾過 | 67 |
| 血液濾過 | 0 |
| オンラインHDF | 695 |
| 血液濾過透析 | 6 |
| 持続的血液濾過透析 | 643 |
| 血漿交換 | 195 |
| 二重膜濾過法 | 8 |
| エンドトキシン吸着 | 6 |
| 血漿分離免疫吸着 | 20 |
| 血漿分離LDL吸着 | 0 |
| 腹水濾過濃縮再静注法 | 643 |
| 顆粒球除去療法 | 42 |
| ■腎移植 | |
| 生体腎 | 9 |
| 死体腎 | 2 |
| ■ブラッドアクセス関連手術 | |
| シャント作成術 | 129 |
| (うち、人工血管を使用したもの) | (22) |
| 動脈表在化 | 14 |
| シャント閉塞術 | 1 |
| 長期留置型カテーテル挿入 | 31 |
| その他のシャント関連手術 | 10 |
| ■腹膜透析関連手術 | |
| テンコフカテーテル挿入術 | 8 |
| テンコフカテーテル出口部形成・変更・入換術 | 3 |
| テンコフカテーテル抜去術 | 4 |
| その他のテンコフカテーテル関連手術 | 1 |
| ■CAPD施行症例数(年度末) | 30 |
いつも地域の先生方におかれましては、聖マリアンナ医科大学病院 腎臓・高血圧内科に患者様をご紹介頂き、誠にありがとうございます。私共としましても、単に大学病院として教育や研究を遂行するだけでなく、地域の基幹病院として、また、地域の医療の最後の砦となるつもりでその役割を精一杯果たし、先生方のお役に立ちたいと考えております。
先生方からご紹介頂く、一人一人の患者様が我々にとっては素晴らしい経験となるものであり、また病院を支える力となります。これからも、是非多くの患者様をご紹介頂ければ幸いです。
先生方に対して失礼の無いように対応するように日頃から教育をしておりますが、若い医師の多い医局でもあり、もしお気づきの点があれば、是非、責任者である柴垣までご連絡頂ければ幸いです。
今後とも聖マリアンナ医科大学病院 腎臓・高血圧内科を何卒よろしくお願い申し上げます。
診療部長 柴垣 有吾
診療科・部門のご案内
-
診療科
-
部門
-
センター
- 救命救急センター
- 夜間急患センター
- リハビリテーションセンター
- 健康診断センター
- 総合周産期母子医療センター
- 生殖医療センター
- 精神療法・ストレスケアセンター
- 腎臓病センター
- 腫瘍センター
- 内視鏡センター
- 超音波センター
- 画像センター
- 放射線治療センター
- 輸血部
- 臨床検査センター
- 手術・IVRセンター
- 集中治療センター
- 中央器材室
認知症(老年精神疾患)治療研究センター
- 統合失調症治療センター
- 呼吸器病センター
- ハートセンター
- 心不全センター
- ハイブリッド心臓大動脈治療センター
- 脳卒中センター
- パーキンソン病治療センター
- 肝疾患医療センター
- 脊椎センター
- 人工関節センター
- こどもセンター
- 内分泌疾患センター
- ゲノム医療推進センター
- 遺伝診療部
- がんゲノム診療部
- 緩和ケアセンター
- 感染症センター
- 糖尿病センター
- てんかんセンター
- 胆道・膵臓病センター
- リウマチ・膠原病生涯治療センター
- 神経内分泌腫瘍センター
- こどものこころセンター